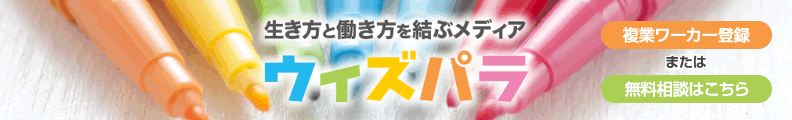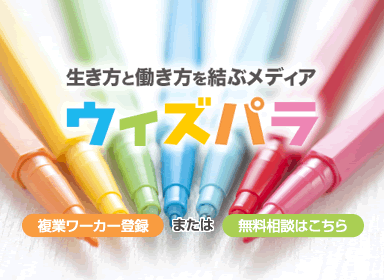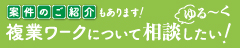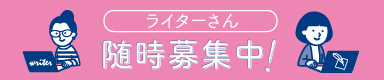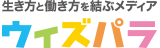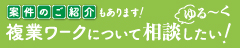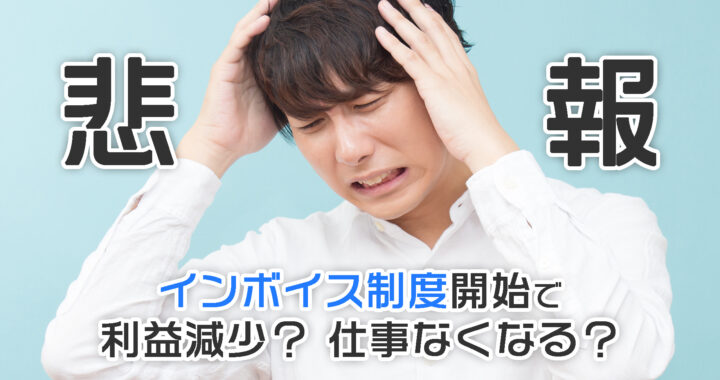「偽装フリーランス」とは!?あなたも都合の良い「偽装フリーランス」になっていませんか?
100の生業を持つ現代版百姓を目指す、破天荒フリーランスのざき山です。
複業メディア「ウィズパラ」では、サラリーマンの方、学生の方、フリーランスの方、問わず、『複業』という、これからの時代の新しい働き方を実現するために必要な知識・ノウハウを発信していきます。
われらが、フリーランス協会さまがSNSにて、最近しきりに注意喚起を行っています。
「偽装フリーランス」に注意!?
とのこと。
「偽装フリーランス」とはなんぞや、初耳です。
言葉のひびき的に、フリーランスと偽ってはたらくオレオレ詐欺のようなものかと思ったのですが、どうやら違うようです。
端的に言うと「偽装フリーランス」とは、
「表面上はフリーランスとの業務委託契約で仕事をしてもらっているが、その実態は、労働者同様の雇用契約になっている状態」のことを指します。
うーん、なるほど。
雇用契約として人を働かせるより、業務委託契約をしている人をいのままに働かせたほうが得だから、実態は社員や契約社員なのにフリーランスということにして働かせようとする、悪知恵のはたらく企業が増えています・・注意しましょうねということでしょうか。
今日は、昨今しきりに注意喚起が始まった「偽装フリーランス」について深堀りしていきたいと思います。
改めて「偽装フリーランス」とはなんぞや?
「偽装フリーランス」とは、労働者のような働き方をしているのに、フリーランスとして扱われている人たちのことを指します。
ちなみに労働者とは、会社と「雇用契約」を結んで、会社の指揮命令を受けて仕事をします。
正社員や有期契約社員、派遣社員、アルバイトなどを全て含みます。
一方のフリーランスは、企業と請負契約などの「業務委託契約」を結んで、発注された仕事をこなす人たちです。
発注者側である会社から最低限の指示は受けますが、仕事を受けるか受けないかの判断、報酬などの条件、仕事の進め方については自由な裁量があります。
両者の大きな違いが、労働基準法など労働法の保護を受けられるか否かです。
労働基準法では、一定の条件を満たした場合に有給休暇を与えたり、時間外労働に対して割増賃金(残業代)を支払ったりするよう規定されています。
また、別の法律においても、最低賃金を支払うことや、仕事上の理由でけがをした際には労災補償を受けられることなども定められています。
ただし、こうした法律の対象になるは「労働者」だけで、フリーランスは、労働基準法など労働法の対象となる「労働者」とは扱われません。
要は労働基準法の保護が及ばないということになります。
「偽装フリーランス」の何が問題なのか、問題点洗い出し
「偽装フリーランス」の問題は、端的に言えば、企業は負うべき責任や金銭負担を負わずに、人材を労働者のように扱うことで、多くの人材が苦痛や負担を余儀なくされているという状況です。
たとえば社員と同じ働き方を強制(勤務時間などを細かく指定)されたりして、本来、フリーランスにあるべき裁量のある働き方や自由が制限されたり・・
社員と同じ働き方を強制されているにもかかわらず、業務上の事由による負傷でも労災が下りなかったり・・
労働時間や残業代の支払いなどが行われなかったり・・・するわけです。
「偽装フリーランス」という認識がなく、圧倒的な弱い立場ゆえに、発注者側の企業の意のままに使われて、いざという時に何の保護も受けられないというケースが増えており、最近では社会問題となっており、国や関係団体が周知の徹底と対策に乗り出している状況です。
やはりフリーランスは社会的な立場が弱く、仕事を特定の会社に依存している状況が多く、会社の意に背くのが難しいというのが「偽装フリーランス」問題の根底にあると思います。
まずは「偽装フリーランス」問題がいかに悪であるか、働かせる側も働く側もふくめ、社会全体で認知を広げる必要があると思います。
ただ逆に、偽造フリーランス防止を気にする企業が保守的になりすぎてオーバーコンプライアンスに陥ったり、フリーランスとの取引自体を回避したりと、企業とフリーランスの双方にとって働きにくく、フリーランス活用をはばむ状況が生まれることも深刻な問題です。
たとえば、取引先の社内規定に「フリーランスはランチや飲み会に誘ってはいけない」という内容があったり、
「会社の方針でフリーランスとの取引は原則できなくなったから派遣契約に切り替えて欲しい」と言われた・・などのケースですね。
うーん・・・難しい問題です。
働かせる側も働く側も法令を熟知し、働かせる側はコンプライアンスに気を使い、働く側は自分の権利を守るために対策を練る必要ががありそうです。
「偽装フリーランス」かどうかの判定ポイント
◆場所的・時間的な拘束がある
たとえば「業務や休憩時間の開始・終了時にタイムカードの打刻や勤怠報告を求められる」などです。
上記の状態は、扱い的にはおもいっきり社員ですよね。
フリーランスといえば、働く場所や働く時間に裁量があるのは、当たり前の話です。
その他には、たとえば・・
◆決まったシフトや当番に基づき働いている
これは、もはやフリーランスというよりはアルバイトっぽいですよね。
◆仕事の進捗をアプリで管理される
全体のプロジェクトの進捗を気にする発注者側としては、作業をしているフリーランスの進捗状況を気にするというのもわからないではないですが・・・
やはり、じぶんの会社の社員のように扱うのはNGでしょう。
◆当初の契約内容にない業務を指示されて断る余地がない
これは、同じフリーランスとして何回も味わってきた状況です。
発注者は仕事の請け手がどんな無茶も聞いてくれると考えているのでしょうか?
仕事を出す側より、仕事を受ける側のほうが立場が弱くなりすぎるというのはあるあるですね・・。
など、上記はほんの一例ですが「偽装フリーランス」に判定されるかもしれないケースです。
「偽装フリーランス」にされないようにフリーランスがとれる対策
◆「偽装フリーランス」がどんな存在であるか、そしてその問題をフリーランス自身が熟知する
まずはフリーランス自身が、「偽装フリーランス」とはなんたるか、そしてなぜズルい企業は「偽装フリーランス」として働かせようとするのか・・・
その闇を熟知しないと何もはじまりませんよね。
国や関係機関が問題の対策に乗り出してくれていますが、やはりじぶんのことは自分で守らないと。
じぶんのお金や働き方・自由・権利が不当に搾取されていると気づかないとダメですよね。
結局、世の中、無知な者は搾取される・・・そういう風にできているんです。
◆収入先の1社集中を回避(収入源を増やす)
じぶんが「偽装フリーランス」のような状況になってしまっているなぁと気づけたとしても、
今の仕事が無くなると生活ができないため、なくなく従わざるを得ないというフリーランスも多いのではないでしょうか?
やはり仕事を出す側が、立場が強く優位な立場から無茶な注文を出し、働く側が従わざるを得ないという構図は、どこにもありますよね。
希望の条件で仕事を獲ることが苦でなければ、「偽装フリーランス」に追い込むような企業からの仕事はスパっと断れるはずです。
経営手法で、あまり多角化は良いイメージは持たれていませんが、フリーランスの働き方を守るという意味においては、収入先・収入源を数多く広げておくのは必須でしょう。
収入が1社に依存している状況は非常にリスキーです。
理不尽な要求を出されたら、きちんと断れるように・・断ったとしても生活に支障が出ることがないように、収入源を分散することがフリーランスには求められます。
そう考えると安定の代名詞であるサラリーマンも収入先を1社のみに絞っている時点で、めちゃくちゃリスクのある生き方と見ることもできますよね。
◆フリーランスを辞め労働者となり、せめて労働基本法の保護を受ける
「偽装フリーランス」は働き方だけ見れば、労働者と大して変わりません。
なのに労働者であれば受けられる福利厚生などの権利だけが、認められていないわけです。
であれば、形ばかりのフリーランスを辞めサラリーマンや派遣社員に組み込んでもらうこともひとつの選択肢では無いかと思います。
せめて働き方が同じなら、受けられるべき正当な権利や保障を得ておこうという考え方ですね。
社員や契約社員・アルバイトにしてもらえるよう会社に伝えても、断られる場合は、意図的に偽装フリーランスを利用している可能性があります。
◆「偽装フリーランス」状態にまきこまれた時の対応策を考えておく
まず自分が「偽装フリーランス」として働かされた事を事前に想定して対策を練っておきましょう。
まずは、前提として下記のことを整理しておきましょう。
・フリーランスのまま働き続けたいのか
・従業員としての待遇となるのがよいのか
・トラブルを契機に、契約自体は解消してもよいのか
フリーランスに関するトラブルに対応するため、国は2020年に「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
第二東京弁護士会が運営を行っており、弁護士から必要な法的アドバイスをもらえる制度になっています。
そのほか自身で信頼できる弁護士を探して相談をしてもよいですし、
労災の問題であれば労働基準監督署等に相談することも考えられます。
フリーランスとしての働き方を継続する前提であれば、不当な取引条件等についての相談として、公正取引委員会の相談窓口に相談することも選択肢のひとつです。
まとめ・・・フリーランスという働き方を守るには知識と強い心が必要・・・対策は練っておこう
フリーランスという存在は、所属する会社という後ろ盾が無いので、じぶんの働き方・権利・お金・自由を守るためには、日ごろから学んだり、情報収集し、すべてじぶんで判断・決断して動かなければなりません。
サラリーマンより自由なフリーランスになろうと安易に考えている人は要注意です。
ただじぶんの裁量で働けるフリーランスという働き方は非常に魅力的で、不断の努力で守るべき価値のあるものです。
日ごろから「偽装フリーランス」のようなフリーランスをはめようとする罠に気を付けて素晴らしいフリーランスライフを送ってください。
みんなの声
昨日から再びよく読まれているこちらの記事。ちなみに、偽装請負と偽装フリーランスは似て非なる問題だったりします☝
偽装請負:労働者派遣契約を締結していないが、実態が「派遣(または労働者供給)」
偽装フリーランス:業務委託扱いにしているが、実態は「直接雇用」https://t.co/0x5jVZpqqs— フリーランス協会/個人事業主・1人社長・副業ワーカー向け情報 (@freelance_jp) May 2, 2024
ネットビジネス系によくある業務委託のやり方の多くは、実はドストレートな法令違反ってのはよくある。
「勤務時間、場所を決める裁量をフリーランスの人から奪っていたり、マニュアルをつくってその手順に従うよう求めたりといったケースは偽装フリーランスとみなされる可能性が高い。」 https://t.co/qADaYr7WLJ
— ロン (@CEO_loves_tech) April 10, 2024
たとえば、開発やデザインなどのクリエイティブ業務で、毎日決まった時間の出社を求めたり、勤怠記録の提出を促したりと、場所や時間を拘束、管理するのはNG
気づけば社員のような働き方に!? 「偽装フリーランス」って何?|フリパラ(フリーランス協会公式note)@frepara_jp https://t.co/KNHQA8oNck
— kunugi design (@kunugidesign) May 2, 2024
どうやったら人を安くこき使うかのアイデアは底なし。
「契約上は業務委託の個人事業主なのに、「配送センターから1日に13時間配送しろと指揮命令されている。フリーランスではない」などと訴えた。」まるで社員、でも有休や残業代なし 守られない「偽装フリーランス」 https://t.co/z98wqodaqd
— ミスターK💙💛 (@arapanman) February 17, 2023
「名ばかりフリーランス」=「偽装フリーランス」
「仕事を断れない」「発注者の指揮監督下にある」「時間や場所を拘束される」などの基準に照らして「労働者性が高い」とみなされば、フリーランスでも、労働法の保護対象となります。
— 安達裕哉 (@Books_Apps) November 2, 2023
偽装フリーランス問題は根が深くて、発注者側はもちろん悪なんだけど、受注者側も自ら進んで労働者性を発揮してる人が多いんだよな。責任感と労働者根性を履き違えてる人とか、技術力が低いから従順な労働者としてダンピングしてる人とか…。
— ゆき@フリーランスWebエンジニア (@yuki80271003) March 17, 2024
偽装フリーランスが葬送のフリーレンに空目するくらいに脳がバグってます。
— 谷内田真也|観光法務の専門家|観光業の外国人雇用支援 (@masayachida) April 19, 2024
この複業ワーク推進メディア「ウィズパラ」を運営する株式会社パラワークス(Wantedly
ページはコチラ)では、優秀なスキルを持つ複業志向を持つ方からのコンタクトを常に募集しております。
デザインスキル・プログラミングスキル・マーケティングスキル・広告運用スキル・ディレクションスキル・ライティングスキルなど必要としているスキルは多種多様。
転職ではなく複業ワークという働き方に興味があるエンジニア・デザイナー・マーケター・ディレクターの方は、ぜひ問い合わせフォームからお声がけください。
ParaWorks社長中村さんの「ウィズパラを運営する僕の”建前”と“本音”」もぜひ合わせてお読みください。思わず連絡したくなりますよ。
この記事を書いた人

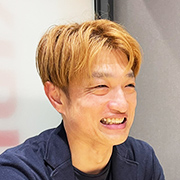
山崎岳史
東京都中野区のフリーランスでWeb制作を行っております。
Web制作会社から独立してから、13年が経ちます。
おもにマークアップやJavascriptのコーディング、Wordpressのカスタマイズなどフロント回りの開発が得意ですが、PHPとMySQLを連携させたシステム開発もよく行います。
ビジネス系メディアへの寄稿などライターとしても活動しています。
自分の最大の売りは、即レススキルと誠実さ(自分で言うなw)だと思います。
最近は、フリーランスや複業(複数の生業を持つ)という働き方の素晴らしさに気づき、この新しい時代の働き方の普及活動をしています。
このメディアでこの変化の早い世の中で、いかにすればフリーランスとして活躍していけるか有益な情報を発信していきます。
この記事を書いた山崎岳史個人に仕事のご依頼やご相談、世間話や飲みのお誘いなどがある場合は、コチラまでお気軽にご連絡ください。
この記事がためになったなぁという人は、SNSで紹介いただいたり、下記のSNSアカウントをフォローしていただけると嬉しいです。