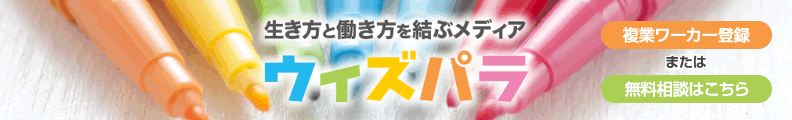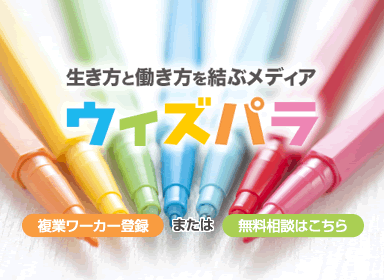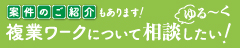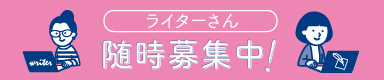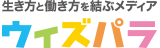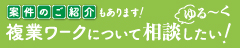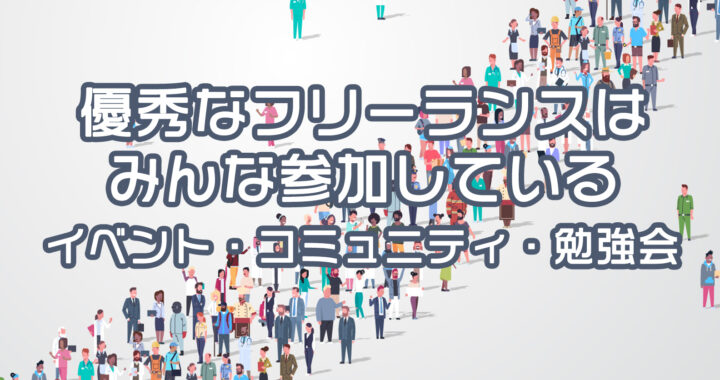シリーズ【ChatGPTとフリーランス】 Vol.3 AIが生成する作品で商売していいの!?AIが生成したコンテンツの著作権はどうなる?
100の生業を持つ現代版百姓を目指す、破天荒フリーランスのざき山です。
複業メディア「ウィズパラ」では、サラリーマンの方、学生の方、フリーランスの方、問わず、『複業』という、これからの時代の新しい働き方を実現するために必要な知識・ノウハウを発信していきます。
最近、Amazonの出版物でAIが生成したグラビアアイドルの写真集や3Dキャラクターの作品集などが並ぶようになっているのに気づきました。
それらの作品のあまりのクォリティの高さに驚かされながら、AIがこの手のコンテンツを生成できるようになるのなら、ギャラを出してグラビアアイドルやカメラマンに依頼する事も、優秀なイラストレーター・3Dモデレーターなどに依頼する機会も減っていき、コンテンツを生み出す人達の仕事が大量に無くなってしまうのではと不安にかられるわけです。
ただAIを使って生成したコンテンツを出版したり、Youtubeなどで配信してマネタイズできるのであれば、AIを駆使する人たちにとってはこんなに素晴らしい事はないなとも、同時に感じます。
ここでひとつ疑問が生じます。
そもそもAIで生成したコンテンツで商売をして良いものなのか・・・?
これらの生成物の著作権、商売の権利はどこに帰結するのか・・?
AIを利用する際に利用規約をこまかに読み込むことも、はずかしながらないので、まったくわからなかったため、これはまずいとこのあたりを調査いたしました。
そもそもAIで生成するコンテンツで商売していいのか?
結論から言うと、AIで生成するコンテンツで商売してもOKです。
ただし、下記のような担保すべき前提条件や守るべきルールや制約を満たす必要があります。
・オリジナリティと付加価値
・著作権など法的な制約
・コンテンツの品質と信頼性
・倫理と透明性
・ユーザーのプライバシーとデータセキュリティ
それではひとつずつ紐解いていきます。
オリジナリティと付加価値
同じAIから生成されるコンテンツは、インプット情報が同じであれば、基本的にはアウトプットは全て同じになります。
そうでなくてもテイストが似通ったりして、同じようなコンテンツの氾濫になりかねません。
AIによって生成されたコンテンツが他のコンテンツと競合しないように、独自性や付加価値を提供する方法を考えることが重要です。
そうでなくては、AIでいくらコンテンツを生成したところで、それらのコンテンツには大して価値は付加されません。
オリジナリティと付加価値を持たせるためには、どのような工夫が必要になるのでしょうか。
■生成コンテンツのカスタマイズ
ユーザーが生成されたコンテンツをカスタマイズできるようにすることで、オリジナリティを持たせます。
例えば、生成されたテキストやデザインに手動で修正や追加を行う機能を提供することで、ユーザーが自分自身のアイデアやスタイルを反映させられるようにします。
またコンテンツ生成前に、ユーザーがウィザードなどで選択肢を選択することで、コンテンツにバリエーションを持たせるなどの工夫も考えられます。
このような工夫が出来れば、同じコンテンツの焼き増しにはならず、ユーザーの満足度は向上します。
■文体やトーンの選択
AIに対して特定の文体やトーンを指定することで、コンテンツのスタイルや雰囲気をカスタマイズできます。
例えば、フォーマルな文章、ユーモアのある文章、専門的な文章など、目的に応じた文体を選択することができます。
動画やイメージであれば、白黒であったりセピアだったり、絵画調だったりアニメ調と指定してコンテンツを出力する訳です。
■ユーザーのフィードバックを活用
ユーザーからのフィードバックを収集し、それをAIのトレーニングに活用することで、ユーザーの好みやニーズに合わせたコンテンツを生成できます。
このフィードバックループを確立することで、オリジナリティを高めつつ、付加価値を提供できます。
AIの学習と一緒ですね、コンテンツを求めるユーザーからのフィードバックを反映するという工夫は何より重要ですね。
■ユーザーの要求やコンテキストに合わせる
これはコンテンツを生成するAIを自ら開発できる場合に限られますが、AIをプログラムする際に、ユーザーの要求やコンテキストに合わせてコンテンツを生成するように設計することが重要になります。
例えば、特定の業界や専門知識に関連するコンテンツを生成するAIを開発する場合、その分野の専門用語やトピックに精通するようにAIをトレーニングすることがオリジナリティを高める手段となります。
■クリエイターがAI生成のプロセスに参加
AIをツールとして使用する際に、クリエイターや専門家がAI生成のプロセスに関与し、AIが生成するコンテンツに独自のアイデアを加えることが重要です。
これにより、AIとクリエイティブな人間の共同作業が可能となり、オリジナリティを高めることができます。
要するに、AIを使用してコンテンツを生成する際には、人間のクリエイティビティと協力し、ユーザーのニーズに合わせた工夫を行うことが重要です。 AIはツールであるため、クリエイターやユーザーがその能力を最大限に引き出すことが鍵となります。
著作権と法的な制約
AIでコンテンツを生成する際の著作権や法的な制約について気を付けるべき重要なポイントがあります。
具体的な法律や規制は国や地域によって異なるため、その地域の法律のプロに法的なアドバイスを受けることが大切になります。
◆著作権のクリアランス
AIを使用してコンテンツを生成する際に、元の素材が他の著作権に違反していないことを確認しなければなりません。
著作権のクリアランスを確保せずに他人の著作物を利用することは法的に問題となります。
◆著作権者とのライセンス契約
AI生成コンテンツを商業目的で使用する場合、元の素材の著作権者と適切なライセンス契約を締結することが必要です。
ライセンス契約は使用許可、利用料金、制約事項などを明示するものです。
◆著作者情報の表示
AI生成コンテンツを使用する際に、元の素材やAIに関する適切な著作者情報を表示することが求められることがあります。
これは著作権法に従った義務です。
◆著作権の創造性
著作権は創造的な作品に適用されますので、AIが単なるデータの生成やルールに従った計算を行うだけの場合などは、そのコンテンツには著作権が認められません。
◆パブリックドメイン※とフェアユース※であっても・・・
パブリックドメインのコンテンツやフェアユースに該当するコンテンツは、一般的に著作権の制約を受けにくいですが、それでも法的な指針に従うことが重要です。
※パブリックドメインとは、知的創作物についての、著作権をはじめとする知的財産権(知的所有権)が発生していない、誰でも利用できる状態のことです。
※フェアユースとは、一定の条件を満たしていれば、著作権者から許可を得なくても、著作物を再利用できることを示した法原理です。
◆AIのトレーニングデータ
AIをトレーニングするために使用されるデータには、ライセンスや著作権に関する問題があることがあります。
データの取り扱いに注意し、適切な権利を確保するか、ライセンスを取得する必要があります。
◆法律の変化に対応する
AI生成コンテンツに関する法律と規制は、テクノロジーの進歩スピードに追いつこうと、日々変遷しています。
最新の情報に基づいて行動し、変更に適応することが大切です。
◆法律のプロからのアドバイスを受け取る
AI生成コンテンツを使用する際には、法的な制約を十分に理解し、遵守することが不可欠です。
法的な問題を避け、著作権者や他の利害関係者の権利を尊重することが重要です。
AI生成コンテンツに関する法的な疑問や問題がある場合、弁護士や法律専門家の助言を受けることをお勧めします。
法的なリスクを最小限に抑えるために役立つでしょう。
コンテンツの品質と信頼性
AIは正確で信頼性のある情報を提供できる場合もありますが、誤った情報を生成することもあるため、生成されたコンテンツを慎重に監視し、修正する必要があります。
ようは、AIがアウトプットする情報は、真実とは違う異なることが往々にしてあり、AIが発するコンテンツをそのままファクトチェックをすることなく、世に発信した場合の責は、AIを使って情報を発信した側に帰することに注意が必要ということです。
よくフェイクニュースで、事実と違う写真や動画が出回る事がありますが、まさにあれですね。
AIを使ってコンテンツを生成する者には、AIを使って誤った情報を世間に発信しないファクトチェックのリテラシーが求められるわけです。
AIがインプットされた情報をどう扱われ管理されるか、まったくわかっていないと、思わぬ情報流出に結びつき大変危険な状態と言わざるを得ません。
倫理と透明性
AIを使用する際には、倫理的な配慮が必要です。
偽の情報を生成したり、人々を欺くことは避けるべきです。
残念ながら一部の国ではAIで生成する偽情報を使ってプロパガンダ映像が作られたりしています。
AIがコンテンツを生成するプロセスを透明にし、ユーザーがAIが関与していることを理解できるようにすることが大切です。
ユーザーのプライバシーとデータセキュリティ
AIを使用してユーザーコンテンツを生成またはカスタマイズする場合、ユーザーのプライバシーとデータセキュリティを守ることが必要になります。
この点については、AIにインプットする情報が、コンテンツ生成者のみであれば、問題ありませんが、AIに不特定多数のユーザーが情報をインプットする場合、その情報のプライバシーとセキュリティの管理は当然のことながら、コンテンツ提供者側に配慮が求められるわけです。
AIで生成するコンテンツの著作権は誰のものなのか?
AIによって生成されたコンテンツの著作権については、国によって異なる法律が存在し、また法的な議論や規制が進行中であるため、一概には言えません。
一般的に以下の要因が影響を与えます。
●制作者(作者)
AIを設計、プログラム、トレーニングした個人や組織は、AIが生成したコンテンツの著作権を主張することができます。
これはAIを開発した人々がAIの”親”であるという立場です。
●著作権の可否
いくつかの国では、著作権は創造的な労力と知的貢献に基づいています。
AIが独自の知的貢献を提供した場合、そのコンテンツに対する著作権が主張される可能性が高まります。
ただし、AIが単にデータから学習したり、アルゴリズムに従って生成した場合、著作権が確立しにくいこともあります。
●法律と規制
各国の著作権法や知的財産法にはAI生成コンテンツに関する規定が含まれていることがあります。
これらの法律は地域によって異なりますが、AI生成コンテンツの著作権について明確な指針を提供しています。
AI生成コンテンツに関する法的な規制が進化しているため、最新の情報に基づいて行動することが求められます。
●利用目的
AI生成コンテンツの著作権は、そのコンテンツがどのように使用されるかによっても変わることがあります。
例えば、教育用途や個人的な使用においては、著作権法の下での使用が制限されないことがある一方、商業利用においては著作権者とのライセンス契約が必要となることがあります。
まとめると、AI生成コンテンツの著作権は複雑で国によって異なります。
法律のプロにアドバイスを受け、最新の法律と規制に対する適切なコンプライアンスを遵守することが重要になります。
みんなの声は
ポケモンGOの背景イラストに生成AIを使った疑惑が出てて、公式の回答も濁すようなものだったから海外で炎上してるらしい
ニュースサイトのトップに記事出てたし、もう日本のコンテンツに対する視線はかなり厳しくなってそう— UMゃーん (@nyanco520) September 2, 2023
正直なところ生成AI使ったコンテンツにはびた一文払いたくないのでちゃんと明記して頂きたい
人が創った物にお金を払いたいので(´−ω−`✋)
生成AIは素晴らしい物らしいので、明記しても払う人は払うでしょう
わざわざ偽って印象悪くしてるのは生成AI推進者の責任でしかないどす— henken (@henken_second) August 28, 2023
日本の知財は汚された。海外に対抗できる日本独自の生成AI開発をしていくなら「優秀なコンテンツを生み出す日本クリエイターの個性や権利を保護」しつつ、進めねばならなかった。なぜ、機械学習ならOK盗んでよし、などという真逆方向へ舵を切ったのか。政府や推進派の方々の狂いっぷりが理解できない
— seinana (@seinanaQD) August 27, 2023
映像系・エンタメ系など、コンテンツそのものを商売道具にしている業界において、画像生成AIを業務で利用する場合、著作権侵害のリスクをどのように考えたら良いのかという質問をよく頂きます。…
— 柿沼 太一 (@tka0120) August 14, 2023
AIが発達すればするほど、AIと競合しにくい3次元世界の商売は安全圏になりうる
AIはコンテンツは作れても物質そのものへの関与はできないから
— おむつ@広告運用者という名のインターネット土方 (@matsui8401) June 15, 2023
aiが本当に多分野に進出してきてるのを見て「あ、これデジタルコンテンツは人間勝てんわ」と思ってリアルめの商売やったり他の事に力入れてるけど正解っぽいなー
既存の仕事は技術革新で駆逐される時があるから革新の波を感じたらすぐ逃げないと
目的は分野の第一人者じゃなくて生活する金欲しいだけ
— Atusi@シフォンケーキ他料理中毒 (@Atsusi1217) May 2, 2023
AIによるコンテンツの生成は今過渡期にあるのかもね
人間も結局似たことをやっていて、たとえば漫画ではピッコマに存在している漫画を見ると、うけたパターンを延々とコピーしているだけというのが露骨に見える。商売でもタピオカや高級パンなんかはそう
そのうちだれも気にしなくなると思う— やまだ (@haigokara) November 2, 2022
まとめ
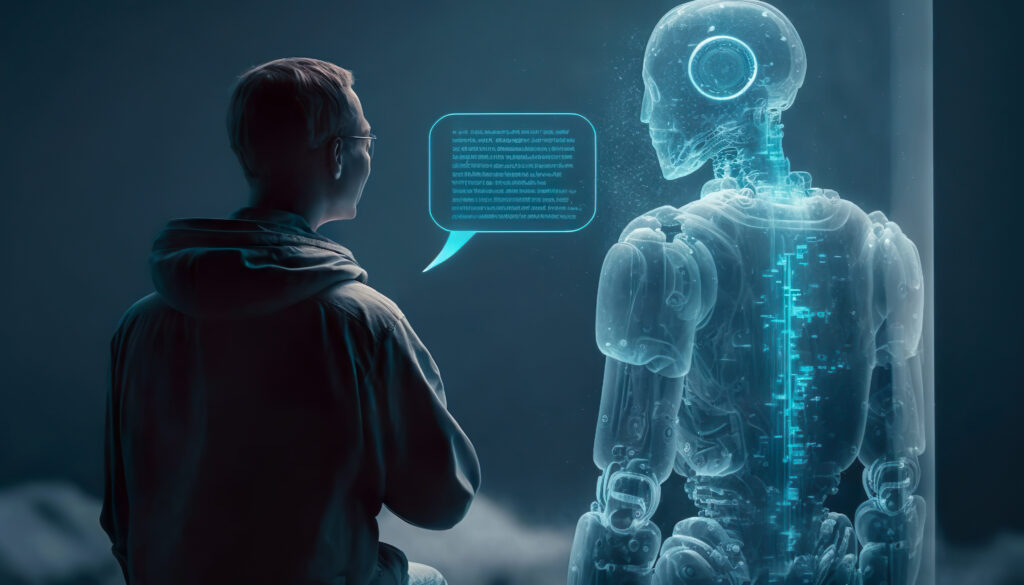
正直、AIを利用したコンテンツのクォリティの高さには目を見張るばかりです。
しかも、その進化は日進月歩・・・人間の手によるコンテンツ作成は、AIには勝てなくなる、いや、もう勝てなくなっているのかもしれませんね。
とはいえ、みんながみんなAIを使った生成物で商売をすれば、同じようなコンテンツの焼き増しにすぎず、そこには価値が生まれないとも考えています。
AIに負けない要素、人間しか獲得できない要素が必ず残るはずです。その武器をコンテンツ生成に落とし込めれば、AIが生成するコンテンツビジネスとの共存は可能なはずです。
また、AIを毛嫌いせずに、人間が苦手な仕事は、積極的にAIに任せ、良いとこどりでコンテンツの質を高めればいい、シンプルにそんな結論に達しました。
この複業ワーク推進メディア「ウィズパラ」を運営する株式会社パラワークス(Wantedly
ページはコチラ)では、優秀なスキルを持つ複業志向を持つ方からのコンタクトを常に募集しております。
デザインスキル・プログラミングスキル・マーケティングスキル・広告運用スキル・ディレクションスキル・ライティングスキルなど必要としているスキルは多種多様。
転職ではなく複業ワークという働き方に興味があるエンジニア・デザイナー・マーケター・ディレクターの方は、ぜひ問い合わせフォームからお声がけください。
ParaWorks社長中村さんの「ウィズパラを運営する僕の”建前”と“本音”」もぜひ合わせてお読みください。思わず連絡したくなりますよ。
この記事を書いた人

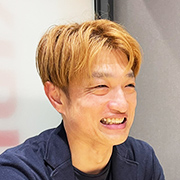
山崎岳史
東京都中野区のフリーランスでWeb制作を行っております。
Web制作会社から独立してから、13年が経ちます。
おもにマークアップやJavascriptのコーディング、Wordpressのカスタマイズなどフロント回りの開発が得意ですが、PHPとMySQLを連携させたシステム開発もよく行います。
ビジネス系メディアへの寄稿などライターとしても活動しています。
自分の最大の売りは、即レススキルと誠実さ(自分で言うなw)だと思います。
最近は、フリーランスや複業(複数の生業を持つ)という働き方の素晴らしさに気づき、この新しい時代の働き方の普及活動をしています。
このメディアでこの変化の早い世の中で、いかにすればフリーランスとして活躍していけるか有益な情報を発信していきます。
この記事を書いた山崎岳史個人に仕事のご依頼やご相談、世間話や飲みのお誘いなどがある場合は、コチラまでお気軽にご連絡ください。
この記事がためになったなぁという人は、SNSで紹介いただいたり、下記のSNSアカウントをフォローしていただけると嬉しいです。