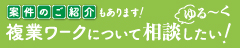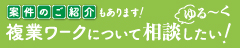副業・複業は税務署に申告が必要?それとも不要?
会社員にとって、副業・複業をすることは「働き方改革」の手段のひとつとして浸透しつつある昨今。
そもそも、会社が副業・複業を禁止する事自体が本来認められないはずですが、実際のところ会社の就業規則に「副業・複業の禁止」と記されているケースが多く、副業・複業のことを相談できないような雰囲気に悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
そんな中でも、会社に隠れて副業・複業を行う方がいるのも事実。当然ながら、会社公認で副業・複業をしたいのが本音なところかもしれません。何れにしても、副業・複業を行う方にとって気になるのが「税務署への申告」。
会社員は基本的に自分で税務署に申告をする必要はありませんが、副業・複業をしている場合は、必ず申告する必要があります。今回は、副業・複業は申告が必要? それとも不要? と気になっている方に向けた内容をお届けいたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
副業・複業が会社にバレてしまう原因は「住民税」?!
副業・複業などの収入が20万円以下なら申告が必要ない、なんて事を一度は耳にしたことがあるかと思います。ただ、この情報には知っておかねければならない基本的な知識があります。
給料以外の所得が20万円以下の場合、発生しない税金は所得税です。しかし、忘れがちなのは住民税の存在。実は、給料以外の所得が20万円以下の場合でも住民税は発生するため、その申告をしなければなりません。
そもそも住民税は、副業・複業で収入がある場合、その収入額に関係なく申告する必要があります。では、どのように申告する必要があるのかをみていきましょう。
住民税は普通徴収に変更するべき?!
住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収とは、会社の給料から天引きにされる納付方法。普通徴収は、自分で納付する方法。
知っておいていただきたいのが、副業・複業の収入で住民税が増えることにより、特別徴収の場合は会社にまとめてその分の額が請求される仕組みになっているという事。会社からすると「なんで会社の収入が増えていないのに、住民税が増えているのだろうか。」と、副業・複業の疑いがある事を察するきっかけが生まれてしまいます。
そのため、申告の際には住民税の納付を「普通徴収」に変更する事が重要です。この方法は確定申告でも住民税の申告でも変わりはなく、申告時の種類に住民税を納付する方法を「自分で納付」に変更するだけで、普通徴収に変えることができます。
ただし、注意しなければならないポイントもあります。それが、役所の存在です。役所としては、住民税をできるだけ特別徴収にしたい方針があるとも言われているので、この点も理解した上で正しい選択をしてみてください。
そもそも申告をしなければいいのでは?

前述した通り、申告することで収入額の変動などが会社にわかってしまうくらいなら、そもそも申告をしないという選択をしたほうが賢いのでは? と思われる方も多いでしょう。給与以外の収入があることを税務署に把握されなければ、特に大きな問題は起きないとも考えられます。
しかし、これは立派な脱税です。
給与以外の収入があるのに申告しない、というのは副業・複業に限らず脱税とみなされ、いわゆる犯罪扱いとされてしまいます。副業・複業自体がバレてしまう事自体が、今勤めている会社からすると信用・信頼問題に発展する可能性が高いのに、脱税まで発覚してしまったら元も子もありません。なので「副業・複業をする」「これからしようと検討している」人たちには、これらの知識をしっかりと持った上で、適宜自分の働き方を選択する必要があると言えるでしょう。
こんな時は普通徴収に変更ができない?!
普通徴収か特別徴収かを選択できる場合を知っておきましょう。固い言葉を使うと「給与・公的年金等に係わる所得以外」です。つまり、アルバイトなどの給与を受け取る副業の場合は、普通徴収の選択ができません。そのため、昼間は会社員、夜はアルバイト! として副業を行う場合は、これまでにお話しした「住民税」の問題に直面する可能性があると言えます。
また、副業・複業が赤字の場合も普通徴収にはできません。
この赤字の分は、会社から特別徴収されている住民税から引かれます。そのため、これまでは「収入が増えていることによる住民税の変動」がポイントでしたが、この場合は「収入が減っていることによる住民税の変動」がポイントになります。いずれにおいても、会社に住民税が変動していることが把握されるきっかけになりますので、この点は十分に把握しておきましょう。
ルールを守った上で「働き方改革」を推進しよう
税金の申告方法はまだまだこれだけではありませんが、まずは基本的な知識や社会的なルールを知ることから始めてみてください。ひとりの働き方がより良くなるだけで、今後の日本は経済的にも社会的にも進化をすることは間違いありません。ルールを守った上で、両者にとって気持ちの良い「働き方改革」を推進していきましょう!